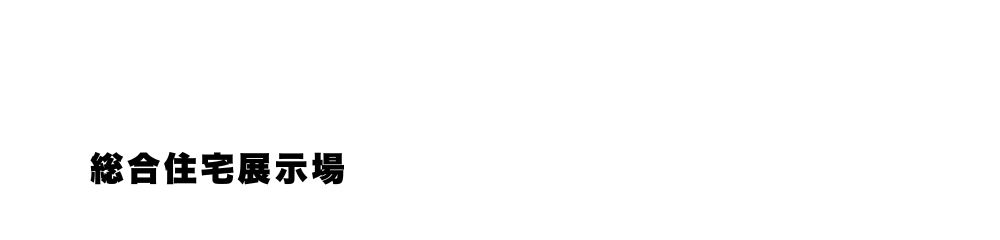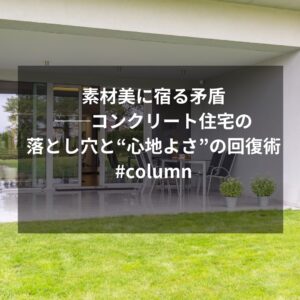“もしも”の前にできること。リフォームで叶える、暮らしと相続のダブル備え #column
「まだまだ元気だから大丈夫」——親世代がそう言っていても、相続のことが少しずつ気になってくる年頃。親の家、どうする?兄弟との分け方は?相続税って高いって聞くけど…?
そんな“ぼんやり不安”に、ひとつのヒントになるのが「相続前のリフォーム」。実はこれ、住みやすさアップだけでなく、相続税の対策としてもメリットがあるかもしれないのです。
この記事では、相続とリフォームがどんなふうに関係するのか、節税につながるパターンとその注意点について、やさしく解説していきます。
この記事を読めばわかること
- 相続税と不動産評価の基本的な関係
- 節税につながるリフォームと、そうでないリフォームの違い
- リフォーム費用と“相続財産”の扱い
- トラブルになりやすい贈与との違い
- 相続前にやっておきたい具体的な準備ステップ
相続税は「遺産総額」しだい。不動産の影響は想像以上に大きい
相続税は、「亡くなった人が残した財産の総額」から基礎控除を引いた金額に対してかかる税金です。
【基礎控除の計算式】 3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
この控除額を超えると、相続税が発生します。
ここで問題になるのが「不動産の価値の判断」。
現金や預貯金と違い、不動産は価値の評価に幅があります。築年数が古くなっている家ほど「これはそんなに価値ないよね?」と感覚的に思ってしまいがちですが、税務上の評価とは別問題。
土地の面積、立地、建物の構造などによって評価は変わり、思っていた以上の額になることも。こうしたギャップが、後のトラブルや想定外の納税負担につながるケースも少なくありません。
「建物の評価額」ってどう決まる?減価償却との関係
相続税の計算で使われる建物の評価額は、「市場での売買価格」ではなく「固定資産税評価額」によって決まります。
この評価額は、建物の構造や築年数に応じて、時間の経過とともに減っていく「減価償却」が考慮されるのが特徴です。
たとえば:
- 築20年の木造住宅 → 評価額はかなり下がっている可能性あり
- RC造(鉄筋コンクリート)住宅 → 耐用年数が長く、比較的評価額が高めに残る傾向
つまり、「古い家だから相続税が高くなるのでは?」という心配はあまり必要ありません。
ただし——その家、リフォームすることで“評価が上がる”可能性もあるのです。
節税になる?ならない?リフォームの内容による“境界線”
では本題。リフォームが相続税にどう影響するのか?ここはポイントをしっかり押さえておきたいところです。
【評価額に影響しにくい=節税効果があるケース】
- 古くなった設備の交換(キッチン・お風呂など)
- 外壁・屋根の修繕や塗装などのメンテナンス工事
- バリアフリーや断熱向上などの改修
→ これらは“元の状態に戻す”ためのリフォームと見なされ、固定資産税評価額に大きな変化はありません。
【評価額が上がる=節税効果に注意が必要なケース】
- 増築(延床面積が増える)
- 高級素材やハイグレードな仕様に変える大規模改修
- 太陽光発電や蓄電池など、新たな機能を追加する設備工事
→ これらは建物の価値を“上乗せ”すると見なされ、評価額アップ→相続税の対象額が増える可能性があります。
つまり、「リフォームすれば節税できる」というのは半分正解で、半分は誤解。内容によって節税になるものと、逆効果になるものがあるんです。

リフォーム費用は“財産から差し引ける”?という考え方
リフォームにかかったお金は、そのまま相続財産から減らせる——という見方もできます。
たとえば、親が自分の預貯金を使ってリフォームした場合:
- 預貯金が減る → 相続財産の中の現金が少なくなる
- かつ、建物の評価額が変わらないリフォームなら、建物価値は据え置き
結果として、“相続時の財産総額”が減ることに。
ただし、注意点もあります:
- 工事内容や金額が“常識的な範囲”にあること
- あからさまな節税目的だと、税務署に否認される可能性も
費用対効果とリスクのバランスをとるには、専門家のサポートが必要です。
「贈与」になってしまうケースに注意。名義とお金の流れがカギ
親の家を子どもがリフォーム。その費用も子どもが負担——このパターン、実は税務上“贈与”と見なされる可能性があります。
【贈与と見なされると…】
- 年間110万円を超える贈与には申告義務が発生
- タイミングや金額によっては、贈与税がかかる
また逆に、親がリフォーム費用を出して、のちのち「これで子に財産を残したつもりだった」と主張しても、それも贈与と見なされるケースがあります。
“相続”と“贈与”の境目はとてもグレー。判断に迷ったら、必ず税理士などの専門家に相談しましょう。
相続にそなえて、今からできる3ステップ
何か起きてからバタバタするよりも、準備しておくことが大切です。
【ステップ1】 家の状態を知る
- 築年数、構造、面積などを把握
- 固定資産税評価証明書を取り寄せておく
【ステップ2】 リフォームの目的を整理する
- 住みやすさ重視? 節税狙い?
- 改修が必要な場所を洗い出し、優先順位を決める
【ステップ3】 専門家に相談する
- 税理士、不動産鑑定士、FPなどへ早めにアプローチ
- 補助金や優遇制度が使えるかも確認
まとめ
リフォームは、住まいを快適にするだけでなく、相続税対策という側面からも有効な一手になることがあります。ただし、工事内容や費用の出どころによっては、むしろ逆効果になることも。
「よかれと思ってやったこと」が、あとから大きな問題にならないように。
家族でしっかり話し合い、プロの知恵を借りながら、未来に備えていきましょう。
住宅展示場では、こうした相続やリフォームに関する相談会や情報展示が開催されていることもあります。暮らしと資産を次世代へつなぐ準備として、まずはできることから動いてみませんか?