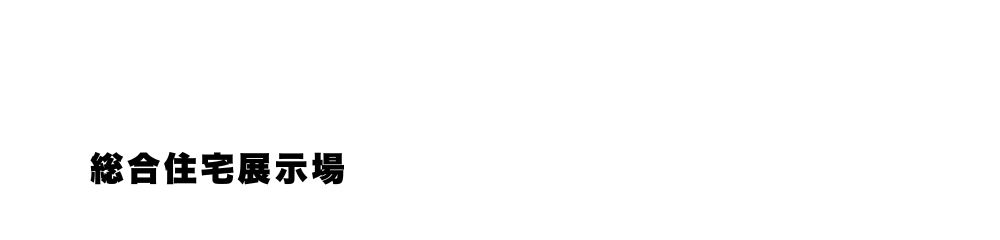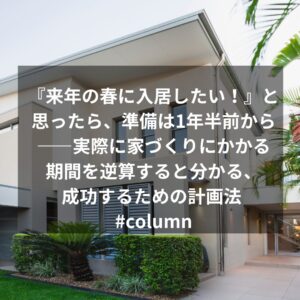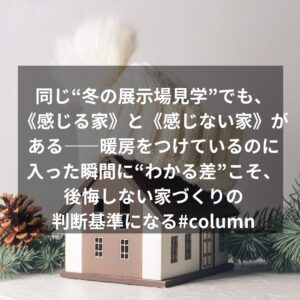飾る場所と隠す場所を分けるだけで、暮らしの質は劇的に上がる —— “メリハリ収納”が部屋の印象を180度変える #column
この記事を読めば分かること
- なぜ「全部隠す収納」や「全部見せる収納」がうまくいかないのか
- “見せる収納”に適したモノと、“隠す収納”に向くモノの違い
- 部屋が洗練されて見える見せ方の工夫
- 生活感をなくしつつ快適に使える隠す収納のテクニック
- 今の暮らしに合った収納バランスを見つける方法
はじめに
あなたの部屋の棚を思い浮かべてください。
お気に入りのマグカップや観葉植物が置かれている一方で、その横には読みかけの雑誌やリモコン、郵便物が積み重なっている……。
片づけたつもりなのに、どこか雑然として見える。
その原因は「見せる収納」と「隠す収納」の境界が曖昧になっていることにあります。
この記事では、収納を「全部隠すか」「全部出すか」の二択ではなく、暮らしの中での“役割”によってメリハリをつける方法を解説します。
読むことで、部屋の雰囲気が変わり、片づけが自然と続く仕組みをつくれるはずです。
1. なぜ「全部隠す」ではダメなのか?
すべてを扉や引き出しにしまい込むと、一見すっきりします。
しかし、毎日使うものまで隠してしまうと「取り出すのが面倒」で結局出しっぱなしに。
→ 結果、「隠す収納」が続かなくなり、逆に散らかる原因になります。

2. 「全部見せる」もうまくいかない理由
逆に、すべてを棚やカウンターに並べる“見せる収納オンリー”も危険です。
色や形がバラバラだと、統一感がなく「生活感のかたまり」に見えてしまいます。
→ 美しく見せられるのは、量を絞った場合だけ。出すモノは厳選が必須です。
3. 何を見せて、何を隠す? —— 判断の基準
- 見せるべきモノ:デザイン性が高い、見て気分が上がる、インテリアとして映えるモノ
(例:お気に入りの器、植物、香りのよいディフューザーなど) - 隠すべきモノ:生活感が強い、形がバラバラ、雑多になりやすいモノ
(例:書類、リモコン、充電器、食品の袋、文房具など)
この区別がつくだけで、部屋の印象は大きく変わります。
4. 見せる収納を成功させる3つのコツ
- 色や素材をそろえる
白・木目・ガラスなど、テーマカラーを決めて統一すると洗練される。 - 空白を残す
棚を埋め尽くさず、あえて余白を残すことで「飾っている」印象に。 - “飾る気持ち”を忘れない
掃除や入れ替えを楽しむ感覚があれば、雑然さを防げます。
5. 隠す収納をストレスなく使うために
- 定位置を決める:同じ種類のモノは必ず同じ場所へ。
- 仕切りやケースで分ける:引き出し内はざっくり分類すると戻しやすい。
- 半透明ケースで中身を見える化:隠すけれど“探さない”工夫。
- 扉裏を有効活用:フックやポケットで小物を収納。
→ 隠す収納は「取り出しやすさ」が命。面倒だと必ず出しっぱなしになります。
6. 実践シーンを想像してみる
夕方、あなたが帰宅してキッチンに立つ。
調味料はラベルを揃えてカウンターに並び、必要なときにサッと手に取れる。
一方で、生活感の強いレジ袋やレシピの切り抜きは扉の内側に隠してある。
外に見える景色はすっきり美しく、隠したモノもすぐに取り出せる——そんな空間なら、料理も気持ちよく進むはずです。
7. あなたに合った“メリハリ収納”を見つけるステップ
- 部屋のモノを「見せたい」「隠したい」に分類する
- 見せたいモノは、色・量・配置を整えてディスプレイ感覚で置く
- 隠したいモノは、ケースや仕切りを活用して“戻すのが楽”な仕組みにする
- 1週間暮らしてみて、違和感があれば調整する
まとめ
収納は「全部出す」か「全部隠す」かの二択ではありません。
見せる収納と隠す収納を使い分けるメリハリが、洗練された空間をつくります。
見せる収納は“飾る意識”を持って厳選し、隠す収納は“仕組み”を整えてストレスをなくす。
この2つを組み合わせることで、部屋はすっきりしながらも温かみのある空間に変わり、暮らし全体が軽やかになります。
今日から、あなたの部屋でも「見せる」と「隠す」のバランスを意識してみませんか?