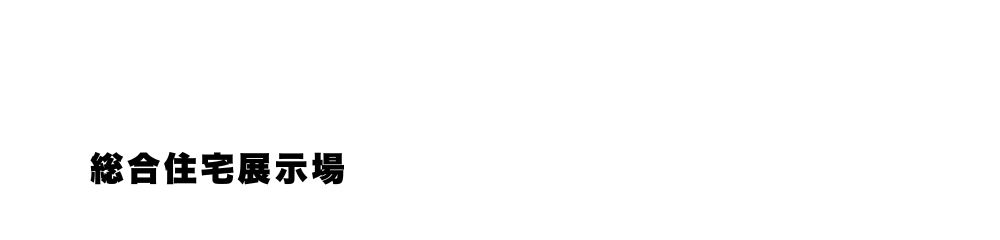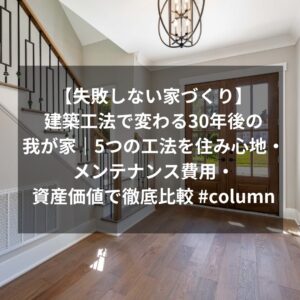新築コンセント計画の真実:住んで3年、毎日「ここにあって良かった」と実感する配置の全技術 #column
この記事を読めば分かること
この記事では、新築住宅のコンセント計画について、以下のことが具体的に分かります。
- 建てる前に絶対やるべき「電化製品の棚卸し」の方法
- 部屋ごとの最適なコンセント数と配置の黄金ルール
- 家具レイアウトとコンセント位置の連動設計テクニック
- 見た目のスッキリ感を実現するコンセント隠しの秘訣
- 将来のライフスタイル変化に対応できる余裕設計の考え方
- 実際に住んで分かった「ここは失敗した」具体例と改善策
はじめに
「そんな細かいこと、後から考えればいいんじゃない?」
注文住宅の打ち合わせで、設計士さんから「コンセントの位置を決めましょう」と言われたとき、私はそう思っていました。間取り、外観、キッチンの設備、お風呂のタイル…決めなければいけないことが次から次へと押し寄せる中、「コンセントくらい、適当でもなんとかなるでしょ」と。
それから3年が経ちました。
毎朝、洗面所でドライヤーを使うとき。夜、ベッドでスマホを充電しながら読書をするとき。週末、ダイニングテーブルでホットプレートを囲むとき。何気ない日常の中で、「あのとき、ちゃんと考えておいて本当に良かった」と感じる場所と、「なんでここにコンセントを付けなかったんだろう」と後悔する場所が、はっきりと見えてきたんです。
コンセントは、確かに地味です。でも、毎日何度も使うものだからこそ、その配置一つで生活の快適さが大きく変わります。延長コードを引き回すストレス、充電のために部屋を行ったり来たりする無駄な動き、見た目を損なうコードの氾濫…これらはすべて、建てる前の「ほんの少しの想像力」で防げたはずなんです。
この記事では、実際に新築に住んで3年の経験から導き出した、コンセント配置の「成功の法則」と「失敗から学んだ教訓」を、あなたにお伝えします。中学生でも理解できるように、専門用語は使わず、具体的な生活シーンを交えながら解説していきますね。
すべての始まりは「電化製品リスト」から
週末の午後、私はリビングのテーブルに大きな紙を広げ、家にあるすべての電化製品を書き出していました。スマホ、タブレット、ノートパソコン、ワイヤレスイヤホン、電動歯ブラシ、電気シェーバー、スマートウォッチ…。
「えっ、こんなに?」
書き出してみて、初めて気づきました。私たち夫婦二人だけでも、充電が必要な機器が15個以上あったんです。
見えない電力需要を可視化する
現代の生活は、想像以上に「充電依存」です。10年前なら、家族一人あたり2〜3個だった充電機器が、今では5〜10個に増えています。
そして重要なのは、これらの機器には「定位置」が必要だということ。スマホは寝室で充電したい。電動歯ブラシは洗面所。ワイヤレスイヤホンはリビングのソファ近く。ノートパソコンは作業デスクで。
この「どこで充電したいか」を明確にしないまま家を建てると、住み始めてから延長コードだらけの生活になってしまいます。
「充電ゾーン」という発想
我が家では、家づくりの段階で「充電ゾーン」という概念を取り入れました。これは、充電機器をグループ化して、それぞれに専用スペースを設ける考え方です。
例えば、玄関近くの棚に「帰宅後充電ゾーン」を作りました。仕事から帰ったら、スマホと会社用スマホをここに置いて充電。リビングにケーブルを持ち込まないので、生活空間がスッキリします。
洗面所には「朝の身支度ゾーン」。電動歯ブラシ、電気シェーバー、ドライヤー用に3口のコンセントを確保。同時に使っても問題ありません。
寝室の枕元には「就寝前リラックスゾーン」。スマホ、タブレット、スマートウォッチ用に2口。読書灯も含めて、快適な就寝環境を整えています。
具体的なリスト作成の手順
あなたも、今すぐできる簡単な作業があります。以下の4ステップで、電化製品リストを作ってみてください。
ステップ1:家族全員の充電機器を書き出す ステップ2:各機器を「毎日使う」「週に数回使う」「たまに使う」に分類 ステップ3:「どこで充電したいか」を決める ステップ4:同じ場所で充電するもの同士をグループ化し、必要な口数を計算
この作業、たった30分程度です。でも、この30分が、今後何十年も続く快適な生活を左右するんです。
生活動線とコンセントの「見えないつながり」
目覚まし時計が鳴る朝6時。あなたはベッドから起き上がり、スマホを充電器から外します。洗面所へ向かい、電動歯ブラシで歯を磨きながら、もう片手でドライヤーの準備。身支度を終えたら、キッチンへ。コーヒーメーカーのスイッチを入れ、トースターにパンをセット。朝食を取りながら、タブレットでニュースをチェック…。
この何気ない朝のルーティンの中に、実は10個以上の「電源接続ポイント」が隠れています。
一日をシミュレーション映像で再生する
家づくりの設計士さんが教えてくれた最高のアドバイスがあります。それは「あなたの一日を、ドキュメンタリー番組のように細かく想像してみる」こと。
朝起きてから夜寝るまで、あなたは家の中でどう動きますか?どの部屋で何をしますか?どんな電化製品を、どのタイミングで使いますか?
頭の中で、自分を主人公にした映画を再生してみるんです。スローモーションで、細部まで。すると、図面を眺めているだけでは絶対に気づけない「不便ポイント」が見えてきます。
階段掃除の盲点
友人から聞いた失敗談があります。彼女の家では、2階建ての階段を掃除するとき、毎回大変な思いをしているそうです。
1階にコンセントを挿して階段を上がっていくと、中段でコードが届かなくなる。仕方なく2階にコンセントを挿し直して、今度は上から下へ掃除。二度手間で、毎週ストレスを感じているとのこと。
「コードレス掃除機を買えば解決するんだけど、もったいなくて…」と彼女は苦笑いしていました。
階段の中段あたり、目立たない位置にコンセントを一つ付けておく。たったこれだけで、この問題は解決します。建てる前なら数千円の追加で済むんです。
水回りの「同時使用」を想定する
洗面所は、意外とコンセント不足になりやすい場所。なぜなら、複数の機器を「同時に使う」シーンが多いから。
朝の忙しい時間、ドライヤーを使いながら、電動歯ブラシを充電したまま、電気シェーバーも使いたい。でもコンセントが2口しかないと、どれかの充電器を抜く必要があります。
毎朝のこの小さな手間が、積み重なると大きなストレスに。我が家では洗面所に4口のコンセントを設置し、さらに鏡の裏側にも隠しコンセントを追加しました。これで朝の身支度がスムーズです。
キッチンは「進化する空間」として設計せよ
3年前、家を建てたとき、我が家のキッチンにあった家電は5つでした。炊飯器、電気ケトル、トースター、電子レンジ、冷蔵庫。これで十分だと思っていました。
今、キッチンには12個の電化製品があります。
新たに仲間入りしたのは、コーヒーメーカー、ホームベーカリー、ハンドブレンダー、電気圧力鍋、フードプロセッサー、ミキサー、ヨーグルトメーカー。そして、食洗機も後から導入しました。
キッチン家電は「増殖」する生き物
キッチン家電が増える理由は明確です。テレビや雑誌で便利な調理家電が紹介され、「これ欲しい!」となる。料理の幅を広げたくて、新しい道具を導入する。健康志向が高まって、専用の機器を買う。
つまり、キッチン家電は「今使っているもの」だけで計算してはいけないんです。「5年後、10年後に増えるもの」まで見越して、コンセントを配置する必要があります。
ゾーン別コンセント戦略
我が家のキッチンは、用途別に3つのゾーンに分けてコンセントを配置しました。
調理台ゾーン(5口):ホームベーカリー、ハンドブレンダー、フードプロセッサーなど、調理中に使う機器用
家電収納ゾーン(4口):炊飯器、電気ケトル、トースター、コーヒーメーカーなど、常設家電用
カップボード下ゾーン(3口):ミキサー、ヨーグルトメーカーなど、時々使う家電の収納&充電用
合計12口。「多すぎでは?」と思うかもしれません。でも今、すべて使い切っています。
隠しコンセントの魔法
キッチンでもう一つ重要なのが、「見た目」です。コンセントやコードが丸見えだと、どんなに素敵なキッチンも台無し。
我が家では、コンセントの取り付け高さを工夫しました。通常は床から25センチの位置に付けますが、カップボードに置く家電用のコンセントは、天板から3センチ下の位置に設置。
すると、炊飯器やケトルの背面にコンセントが完全に隠れ、正面から見てもコードがほとんど見えません。この「3センチの差」が、見た目の印象を大きく変えるんです。
設計段階で、設計士さんに「ここに置く家電の高さは何センチなので、コンセントはこの位置に」と具体的に伝えることが大切です。
在宅ワーク空間は「電源の戦場」
「ちょっと待って、コンセント足りない…」
在宅ワークが始まって最初の週、私はデスクの前で途方に暮れていました。ノートパソコン、外付けモニター2台、デスクライト、スマホ充電器、会社用スマホ充電器、ワイヤレスイヤホン充電スタンド、ウェブカメラ、外付けマイク…。
コンセントを6口用意していたのに、全然足りなかったんです。
リモートワークが変えた電源需要
パンデミック前、パソコンデスクに必要なコンセントは2〜3口でした。パソコンとデスクライトがあれば十分。
でも今は違います。オンライン会議が日常になり、画質と音質を向上させるために周辺機器が増えました。仕事用と私用のスマホを両方充電し、タブレットも使う。バックアップ用の外付けハードディスクも接続。
子どもたちも、学校から配布されたタブレットと自宅用のタブレット、両方を使います。オンライン授業中は、親も静かな別の部屋で仕事をする必要があり、家の中に複数のワークスペースが必要に。
一人あたり、最低でも6〜8口のコンセントが必要です。家族が多ければ、さらに増えます。
コードを隠す設計が集中力を高める
もう一つ、在宅ワークで重要なのが「視覚的なスッキリ感」。
夫の書斎は、机を壁に向けて配置し、コンセントは床から10センチの低い位置に8口並べました。コード類は机の下に落ちて隠れ、作業中の視界には入りません。
一方、私のワークスペースはリビングの一角にあるオープンなカウンターデスク。明るくて開放的ですが、コードが丸見えで、正直気になります。
今から変更するなら、カウンターの天板と同じ高さの位置にコンセントを付けるか、カウンター背面に配線モールを設置して隠したかった。そうすれば、リビングから見てもスッキリした印象になったはずです。
将来の機器増加も計算に入れる
テクノロジーは進化し続けます。今は使っていなくても、数年後には新しいガジェットが登場するかもしれません。
VRゴーグル、スマートグラス、AI搭載のデバイス…。これらを充電・接続するためのコンセントも必要になります。
だから、ワークスペースには「今必要な数+3口」を基本に考えましょう。この余裕が、将来の変化に対応できる柔軟性を生みます。
くつろぎ空間こそ電源の「隠れた主役」
日曜日の午後3時。あなたはリビングのソファに深く身を沈め、お気に入りの小説を読んでいます。手元のサイドテーブルには、温かいコーヒー。足元には柔らかいブランケット。完璧なリラックスタイム…のはずが、スマホの充電が5%に。
でも、コンセントはソファから3メートル離れた壁にあります。立ち上がって充電ケーブルを取りに行く?それとも充電は諦めて、このまま読書を続ける?
こんな小さな不便が、せっかくのリラックスタイムを台無しにするんです。
長時間滞在エリアの法則
ソファ周りとベッド周りには、ある共通の法則があります。それは「長時間過ごす場所ほど、電源需要が高い」ということ。
リビングのソファでは、こんなことをします。
- スマホを充電しながらSNSチェック
- タブレットで動画配信サービスを視聴
- Bluetoothスピーカーで音楽を楽しむ
- 冬は足元に小型ヒーターを置く
- 読書灯で本を読む
- ノートパソコンで軽作業
これだけで、最低5〜6口のコンセントが必要です。
寝室のベッド周りも同様。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、間接照明、加湿器、空気清浄機…。快適な睡眠環境を整えるために、意外と多くの機器を使っています。

家具配置の「リアルサイズシミュレーション」
我が家の最大の失敗は、ソファの配置を正確に想定していなかったこと。
図面上では「この辺にソファを置く」と大まかに決めていましたが、実際のソファのサイズを細かく測っていませんでした。その結果、ソファの真後ろにコンセントが来てしまい、完全に隠れて使えない状態に。
これを防ぐには、購入予定の家具のサイズ(幅、奥行き、高さ)を事前に調べ、図面に正確に書き込むこと。そして、壁からどれくらい離して置くかも含めて計画することです。
方眼紙に縮尺を合わせて書き込むと、より正確にシミュレーションできます。デジタルが得意な人は、無料の間取りアプリを使うのもおすすめです。
床コンセントの賢い活用
ソファの近くに壁コンセントが付けられない場合、床埋め込み式のコンセントという選択肢があります。
床に直接設置するタイプで、普段は蓋を閉じておけば、上を歩いても問題ありません。ソファの真横や、コーヒーテーブルの近くに設置すれば、延長コードを引き回す必要がなくなります。
ただし、床コンセントには注意点も。一度設置すると位置を変えられないので、家具の配置が固定されます。将来的に模様替えをする可能性がある場合は、慎重に検討しましょう。
ダイニングテーブルは「多目的ステージ」
土曜日の夜、ダイニングテーブルは賑やかです。ホットプレートでチーズダッカルビを作りながら、子どもたちはタブレットで音楽を流し、私はスマホで料理の次のステップをチェック。夫はノートパソコンで明日の準備をしています。
そう、現代のダイニングテーブルは、もはや「食事だけの場所」ではないんです。
ダイニングの多機能化に対応する
ダイニングテーブルで起こる電力を使う活動を挙げてみましょう。
- ホットプレートで焼肉、たこ焼き、パンケーキ
- IH調理器で鍋料理
- 電気グリルで焼き鳥
- 子どもたちのタブレット学習
- 在宅ワークのパソコン作業
- スマホやタブレットの充電
- 電動かき氷機やミキサー
これだけ多様な用途があるのに、コンセントが近くになかったらどうでしょう?延長コードを引っ張ってくることになり、家族の足に引っかかる危険も。
3つの設置方法と選び方
ダイニング用コンセントには、設置方法が大きく3つあります。
方法1:壁面設置型
最も一般的で安価。テーブルから一番近い壁に設置します。追加費用が少なく、施工も簡単。ただし、コードが床を這うので、引っかかりやすい。
方法2:床埋め込み型
テーブルの真下に設置するタイプ。コードが最短で済み、見た目もスマート。ただし、テーブルの位置を変えられなくなるのがデメリット。模様替え好きな方には不向き。
方法3:テーブル高さ埋め込み型
壁面をくり抜いて、テーブルの高さと同じ位置に設置。上からコードを挿すので、床を這わない。見た目が最も美しいですが、設置できる壁の構造が限られ、費用も高め。
我が家は方法1を選びましたが、コンセントの位置をテーブルの角から最短距離になるよう計算しました。コードを斜めに這わせると長くなり、引っかかりやすくなるので、最短ルートを確保することが大切です。
子ども部屋は「10年計画」で考える
小学1年生の息子の部屋を覗くと、ベッドとおもちゃ箱、そして小さな本棚があるだけ。シンプルで可愛らしい空間です。
でも、この部屋のコンセント配置を決めるとき、私は「10年後」を想像しました。息子が高校生になったとき、この部屋はどうなっているだろう?
成長と共に変化する電力需要
子どもの成長段階別に、必要な電化製品を想像してみましょう。
小学校低学年
- デスクライト
- 目覚まし時計
- ベッドの読書灯
- たまにタブレット充電
必要コンセント数:3〜4口
小学校高学年
- 上記に加えて
- 学校配布のタブレット充電
- 自宅用タブレット
- 電子辞書
- 音楽プレーヤー
必要コンセント数:5〜6口
中学・高校生
- 上記に加えて
- スマートフォン
- ノートパソコン
- ゲーム機
- スマートスピーカー
- 扇風機やヒーター
必要コンセント数:7〜10口
この変化を見越して、子ども部屋には「今は多すぎる」と感じるくらいのコンセントを付けておくべきなんです。
2パターン家具配置対応設計
子ども部屋の家具は、ある程度パターンが決まっています。ベッド、学習机、本棚、クローゼット。問題は「どこに配置するか」です。
窓の位置、ドアの位置、部屋の形によって、ベストな配置は変わります。さらに、子どもの成長や好みに応じて、模様替えをする可能性も。
だから、複数のパターンを想定しましょう。
パターンA:窓際デスク配置
- 窓際に学習机を配置
- 反対側の壁にベッド
- 机周辺に5口、ベッド周辺に3口
パターンB:壁際デスク配置
- 入口側の壁に学習机
- 窓際にベッド
- 机周辺に5口、ベッド周辺に3口
このように、どちらのパターンでも使いやすい位置に、分散してコンセントを配置するんです。
我が家の娘の部屋は、このパターン想定が甘かったため、机の真後ろにコンセントが来てしまいました。延長コードを横に伸ばして使っていますが、コードの存在感が気になります。
兄弟姉妹がいる場合の特別対応
二人以上の子どもが同じ部屋を使う場合、コンセント数は1.5倍〜2倍必要です。
それぞれが独立して勉強、睡眠、娯楽のスペースを持つため、電源も個別に必要になるからです。将来的に部屋を仕切って個室にする可能性も考えて、各エリアにバランスよく配置しましょう。
通信機器とコンセントを「見せない技術」
友人の家を訪れたとき、リビングの隅に置かれた小さなラックが目に入りました。そこには、Wi-Fiルーター、モデム、そして絡まったケーブルがごちゃごちゃと…。せっかくおしゃれなインテリアなのに、あの一角だけが生活感丸出しでもったいないと感じました。
インフラを隠す発想
インターネット機器は、現代生活に不可欠。でも、見た目は決して美しくありません。点滅するLEDランプ、無骨なデザイン、複雑に絡まったケーブル…。
だからこそ、これらは「見えない場所」に設置するのがベストです。
我が家では、主寝室のウォークインクローゼットの一角に、通信機器専用のスペースを作りました。小さな棚板を設置し、その上にWi-Fiルーターとモデムを配置。コンセントは棚の背面に4口設置。
クローゼットの扉を閉めれば、完全に見えません。でも、家じゅうどこでもWi-Fiの電波は問題なく届きます。
収納内コンセントの活用アイデア
通信機器以外にも、「見せたくない」「でも電源が必要」なものは意外とあります。
玄関シューズクローゼット内
- 電動自転車のバッテリー充電
- コードレス掃除機の充電スタンド
- 傘の乾燥機
パントリー内
- ホームベーカリー(使わないときは収納)
- ヨーグルトメーカー
- 充電式のハンディクリーナー
リビング収納内
- ルンバのホームベース
- 家族のスマホ・タブレット充電ステーション
- モバイルバッテリー充電コーナー
収納の中にコンセントを付けるだけで、生活感のあるものを隠しながら、使いやすさも確保できます。扉を開ければすぐ使える。使わないときは隠せる。この「ちょうど良い距離感」が、快適な暮らしを作るんです。
通気性への配慮を忘れずに
ただし、収納内に電化製品を置く場合、通気性には注意が必要です。熱を持つ機器を密閉空間に置くと、故障の原因になります。
Wi-Fiルーターやモデムは比較的熱を持ちやすいので、クローゼットに換気用の小さな穴を開けたり、扉に通気グリルを付けたりする工夫が必要です。
我が家のクローゼットは、下部に5センチほどの隙間があり、自然に空気が流れる構造になっています。この小さな配慮が、機器の寿命を延ばします。
エアコンコンセントに隠された美学
「エアコンのコンセント?そんなの気にしたことない」
そう思うかもしれません。でも、一度意識すると、気になって仕方なくなるんです。
エアコン本体は壁の高い位置に設置されます。そして、そのコンセントも高い位置に。つまり、ソファやダイニングテーブルに座ったとき、ちょうど目線の高さに来るんです。
白い壁に白いコンセント。そこから垂れ下がるコード。地味だけど、確実に視界に入ります。
天井付けという選択肢
我が家の設計士さんが提案してくれたのが、「エアコンコンセントの天井付け」という方法。
通常は壁面に付けるコンセントを、天井面に設置するんです。すると、エアコン本体の真上にコンセントが来るため、下から見上げてもエアコンの影に隠れてほとんど見えません。コードも極端に短くなり、目立ちません。
追加費用は、一箇所あたり5,000円程度。でも、この投資で得られる「視覚的なスッキリ感」は、金額以上の価値があります。
部屋の格が上がる小さな工夫
特にリビングや主寝室など、インテリアにこだわりたい部屋では、こうした細部への配慮が全体の印象を左右します。
高級ホテルの部屋がスッキリして見えるのは、こうした「見えない工夫」の積み重ねなんです。コード類を徹底的に隠し、視界に入る要素を最小限にする。
あなたの家も、同じ発想で設計すれば、まるでホテルのような洗練された空間になります。
アクセントクロスとコンセントの「調和の科学」
新築のショールームで、私は一目惚れしました。深いネイビーブルーのアクセントクロス。「これを寝室の一面に使いたい!」と即決し、設計に反映してもらいました。
引き渡しの日、ワクワクしながら寝室に入ると…あれ?何か違和感が。
ネイビーの壁に、真っ白なコンセントが3つ。まるで壁に貼られた白い付箋のように、くっきりと目立っていたんです。
コンセントは「壁の一部」として考える
標準的なコンセントカバーは白色。だから、白い壁なら目立ちません。でも、色付きの壁紙やアクセントクロスに白いコンセントを付けると、どうしても浮いて見えます。
これを防ぐ方法は3つ。
方法1:色を合わせる
コンセントカバーを、壁の色に近いものに交換。ネイビーならグレーやダークグレー、ブラウンの壁ならベージュやブラウン。完全に同じ色でなくても、近い色相なら目立ちにくくなります。
方法2:位置で隠す
アクセントクロスを使う壁には、できるだけコンセントを付けない。または、ベッドやチェストなど家具で隠れる位置に配置する。
方法3:デザイン性で見せる
逆転の発想で、おしゃれなデザインのコンセントカバーを選び、インテリアの一部として「見せる」。真鍮製、木製、レザー調など、さまざまなデザインがあります。
我が家は引き渡し後、方法1でコンセントカバーをグレーに交換しました。これだけで、違和感が大幅に減りました。
全体デザインの一部として計画する
アクセントクロスを選ぶとき、同時に考えるべきこと。
- その壁にコンセントはいくつ必要か?
- どの高さに付けるか?
- コンセントカバーの色はどうするか?
- スイッチプレートの色も合わせるか?
これらを「壁のトータルデザイン」として、セットで計画するんです。おしゃれな家は、こうした細部まで気を配っているから、おしゃれなんです。
完璧を目指すシミュレーションの方法論
家を建てて3年。今、過去の自分にアドバイスできるとしたら、こう伝えます。
「コンセント配置のシミュレーションは、『やりすぎ』なんてことはない。徹底的にやって」
素人でも到達できる最適解
家づくりには、専門知識が必要な領域がたくさんあります。構造計算、断熱性能、配管設計、電気配線の容量計算…これらは、プロに任せるしかありません。
でも、コンセントは違います。
あなた自身の生活を、あなた以上に知っている人はいません。どこで何をするか、どんな機器をどう使うか。それを一番よく分かっているのは、あなたなんです。
だから、コンセント配置は、家づくり初心者でも「最適解」に到達できる数少ない領域。逆に言えば、ここを疎かにするのは、もったいない。
「迷ったら設置」の経済学
コンセントを1口増やすコストは、建築前なら3,000〜5,000円程度。場所によってはもっと安いこともあります。
でも、建築後に追加するとどうでしょう?
壁に穴を開け、配線を通し、内装を修復する電気工事が必要。費用は3万〜5万円。場所によっては10万円を超えることも。
つまり、建てる前と後では、10倍以上のコスト差があるんです。
だから、迷ったら付ける。「ここにあったら便利かも…でも使わないかな?」と思ったら、付けておく。使わなくても害はありませんが、なくて困ることは大いにあります。
実践的チェックリスト作成法
最後に、あなたが今日からできる具体的なアクションプランをお伝えします。
ステップ1:部屋ごとの機器リスト 全ての部屋について、使う電化製品をリストアップ。現在持っているものだけでなく、「将来買いたいもの」も含めて。
ステップ2:使用頻度の分類 各機器を「毎日使う」「週に数回」「月に数回」に分類。使用頻度が高いものほど、アクセスしやすい場所にコンセントを。
ステップ3:配置の具体化 方眼紙か間取りアプリで、家具の配置を実寸で書き込む。そして、各電化製品をどこに置くか、マークする。
ステップ4:コンセント位置の決定 電化製品の位置から、最適なコンセント位置を決定。高さも含めて。
ステップ5:余裕の追加 計算した数に、各部屋プラス2〜3口を追加。将来の変化に対応するバッファとして。
この作業、全部屋やっても半日あれば十分です。でも、この半日が、今後何十年もの快適な暮らしを左右するんです。
まとめ
コンセント配置は、新築計画の中で最も「地味」に見える要素かもしれません。でも、実際に住み始めると、その重要性が骨身に染みて分かります。
毎朝の身支度、毎日の料理、在宅ワーク、家族団らん、就寝前のリラックスタイム…あらゆる生活シーンで、コンセントは「縁の下の力持ち」として働いています。
この記事で伝えた成功の法則
- 全ての充電機器をリストアップし、「充電ゾーン」を設計する
- 一日の生活動線を映画のように詳細にシミュレーションする
- 掃除機のコード長さと階段の関係を確認する
- キッチンは5年後の家電増加を見越して余裕を持つ
- カップボード用コンセントは高さを下げて隠す工夫を
- ワークスペースは一人あたり6〜8口を基本に
- コード類を視界から隠す設計で集中力アップ
- ソファ周りに4〜5口、快適なくつろぎ空間を
- 家具配置を実寸でシミュレーションし、隠れるコンセントをゼロに
- ベッドサイドは手が届く高さと位置に設計
- ダイニングは用途に合わせて壁面・床面・テーブル高から選択
- 子ども部屋は10年後の成長を見据えて多めに配置
- 家具配置2パターンを想定し、柔軟性を確保
- 通信機器は収納内に隠して生活感を消す
- エアコンコンセントは天井付けで視覚的にスッキリ
- アクセントクロスとコンセントの色を調和させる
- 迷ったら設置する「余裕設計」が後悔を防ぐ
建てる前の今だからこそ、じっくり時間をかけて考える価値があります。図面とにらめっこし、実際の生活を想像し、細部まで詰めていく。
その過程は、同時に「これからの暮らし」を具体的に描くワクワクする時間でもあります。あなたがどんな暮らしをしたいのか、どんな時間を大切にしたいのか。コンセント配置を考えることは、そんな本質的な問いに向き合うことでもあるんです。
あなたの新しい家が、毎日「ここにコンセントがあって良かった」と感じられる、快適で美しい空間になりますように。